*京都市立芸術大学美術学部同窓会誌『象』第25号 2005年3月発行 pp.17-26
宇宙/芸術/生命 —「宇宙への芸術的アプローチ」補遺—
(1)宇宙飛行士との交流
(2)宇宙絵画
私たち「宇宙への芸術的アプローチ(Artistic Approaches to Space=AAS)」研究グループと宇宙航空研究開発機構(JAXA、旧宇宙開発事業団NASDA)の共同研究が、昨秋の研究報告会「宇宙のこころ、地球のこころ」(2004年11月22日)をもって一応の終結を見た。共同研究というかたちでは2001~2003年の3年間だったが、そもそもは「国際宇宙ステーションの日本実験棟を人文社会科学的見地、とりわけ芸術という視点からどう利用するか」という研究の一環として1996年に始まったから、あしかけ8年に及んだことになる。 私たちの研究と提案は、報告会で配布したCD-ROM形式の報告書にほぼ網羅されている。以下では、参加メンバーの一人として、報告書には明示されなかった研究上の要点ないし問題と、印象に残った宇宙飛行士の言葉を記しておきたい。
宇宙飛行士との交流
古今東西、芸術の中にはずいぶんと宇宙的な現象やイメージがちりばめられているが、私たちの関心は、そうした観念的・イメージ的な「宇宙芸術」ではなく、高度400kmを周回するシャトルや宇宙ステーション内のリアルな空間に置かれた。芸術の研究は、言葉だけの論述や思弁ではなく、具体的な創作実践を通じてのみ可能であるから、JAXAから提供される情報や機会を利用して、さまざまな取材と実験、試作と提案を行なうことが「研究」の内実となった。 とはいえ、これまで実際に交差することのなかった宇宙開発と芸術という異ジャンルが交わりあうために、研究内容面でも体制面でもさまざまな障害やすれ違いが生じた。これらは研究の枠組を大きく規制したが、今後のためにも主な問題点を明らかにしておきたい。
第一に――本学同窓の方々に訴えておきたいことでもあるが――京都芸大には、どの大学にも用意されている外部機関との共同研究の制度がなく、受託研究費の窓口すら存在しなかったということである。共同研究というのは、双方が契約に基づいて研究費を出資して行なうのが当然で、本学と並行して同じ研究を行なっていた東京芸大はJAXA側と同額の研究費を出していた。だが、本学の場合、京都市も大学もいっさい研究費を出さないうえに、JAXAからの研究費は京都市に入り、そこから5%差し引かれてようやく私たちに回ってくる。そもそも教員には個人研究費もなく、「共同研究費」という名目であてがわれるものも授業用の消耗品でかき消える極少額だから、「研究」にまわすどころではない。要するに本学は、実質的には研究を主とする「大学」ではなく、作家が教育者として寄り集まった「学校」にすぎない。だから、大学としてまともな「共同研究」を行なうことができないという驚くべき体制になっていたのだ。「学校」であれば、「教師」は教えればいいだけで「研究」など必要ない――そんな暗黙の認識が内外に浸透しているのだろうか。
第二に、国際宇宙ステーションのイニシャチブはアメリカのNASAがとっているので、スケジュールも実験内容も思うように事は運ばない。例えば、NASAの認可なしにスペースシャトルに芸術実験のための用具や素材を積むことができない。安全確保のため、絵具も粘土もだめである。飲食物を含めて、機内にある既存のものを転用するしかない。また、NASDA/JAXAの要請に応えてさまざまな提案や試作を行なっても、実行段階に移されることはなく、評価などの反応すら返ってこない。科学実験とちがって、芸術上のアイデアや実験は客観的な評価が下しにくいのは仕方ないとはいえ、実現に向かうリアリティのない状況は意欲をそぐ。加えて契約手続きが毎年半年近く遅れ、研究も不安定なスケジュールに振り回されて断続的になる。こうしたことは何人かの初期メンバーの離反を招く一因になった。 あとでわかったことだが、芸術領域と初めて接するNASDA/JAXAにとっては、実現可能性を検討することより、芸術領域からの提案を幅広く受けるだけで当面は十分であり、とりあえずは「宇宙環境の人文社会的利用」の口実になる。宇宙開発という莫大な予算を使う事業には、国や国民を説得するために、理工系一辺倒とは異なる顔つきが必要というわけだった。
第三に、これが根本的な問題だが、芸術が地上環境での重力や光、またそれに対応する人間の知覚経験という基本条件のもとに成立している以上、宇宙における芸術も宇宙環境固有の条件とそれに対応する人間の経験を前提とする。しかし、私たち自身が宇宙を体験しえない以上、この前提の把握も間接的かつ部分的なものにとどまらざるをえない。例えば、宇宙ステーションやスペースシャトルの中の閉鎖的な微小重力環境とは、実際にはどのようなものであり、そこで人間や物質がどのような物理的・心理的状況におかれるのかが、リアルに掴めないのである。
こうした制約の中で私たちがとった方法は、宇宙飛行士との直接的な連携を研究の基軸とすることだった。宇宙環境を実際に体験し、そこで何かを行なえるのは宇宙飛行士だけである。彼らとの交流を通じて宇宙環境の実態を探ること、彼らの宇宙での生活や表現活動のためのツールやプログラムを開発・提案すること、そこからフィードバックして人間存在や芸術の原質を新しい角度から捉え直すこと――こうした探求プロセス総体を「宇宙への芸術的アプローチ」と位置づけたのである。幸いにも、JAXA側は芸術を宇宙環境の人文社会的利用の最前線に位置づけるようになっていたので、私たちの申し出に応じて宇宙飛行士との交流の場を積極的に提供してくれた。
宇宙飛行士たちは、いずれもすぐれた科学者/技術者であるだけでなく、快活・明敏で好奇心にあふれ、生死のかかる現場で仕事する人間の気概に富み、すぐに率直に意見を交わすことができるようになった。次に、私たちの提案をもとにした土井飛行士による日本初の宇宙での絵画実験の実相に触れておく。
宇宙絵画
1997年9月、突然NASDAの担当者から、「11月にスペースシャトルに搭乗する土井飛行士が宇宙で絵を描きたいと言っているので、放映用のシナリオを作成してほしい」と依頼があった。使い始めてまもないEメールでさっそく交渉を始めたが、このときに国境を越えて迅速に情報を交換できる電子コミュニケーションの重要性や、宇宙での活動における多大な制約を思い知った。微小重力下での絵具の浸透や発色効果などを知りたかったが、液体は飛散すると危険なため持ち込みが許可されない。使用が許されたのは、子供が口にいれても大丈夫という大豆油脂性のクレヨンだけだった。私たちと東京芸大が出したいくつかのシナリオ案の中から、最終的に採用されたのは、私たちのプラン「天井のスケッチ」だった。

土井飛行士による宇宙絵画、紙にクレヨン( > AAS 1996-2000報告書)
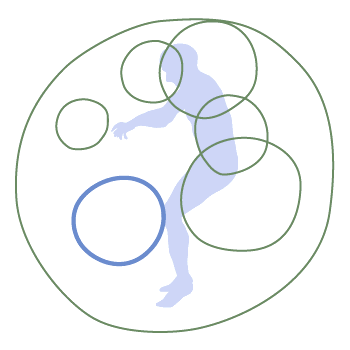
宇宙絵画の分析アニメーションから( > AAS 1996-2000報告書)
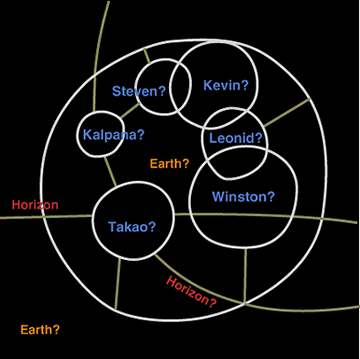
宇宙絵画の分析( > AAS 1996-2000報告書)
このプランは二つからなり、一つは自由描写、もう一つは宇宙での空間感覚の変容を探る「点・線・面:宇宙絵画の基礎実験」というものである。後者のインストラクションの具体性が土井氏の興味を誘ったと思われる。内容は以下の通りである。
以下の一連の作業によって、絵を描いて下さい。画材はすべて自由とし、異なる画材を混用してもかまいません。身体は固定しない状態にして下さい。:
(1) 紙を4枚ないし6枚つないで大きな長方形の紙面を作る。 紙は無地が前提。
(2)その紙いっぱいに大きな円を描く。色は自由。
(3)円に沿って紙を切る。ハサミがない場合は手で破る。きれいに破れなくてもよい。
(4)その円の中に好きな色で「水平線」を描く。そのときの自分の身体の感じを大切にして描くこと。画材は自由。「水平線」をどう解釈するかも自由。
(5)その円の中に「上昇する6つの輪」を描く。漫画のような補助的な線は描かずに、輪どうし、また輪と水平線を関係づけることによって上昇感を表す。
輪の大きさや色はそれぞれ自由。互いに重なってもかまわない。 6は搭乗する飛行士の人数。
(6)円の中の任意の箇所を好きな色で塗りつぶす。 塗り残しがあっても気にする必要はない。
タイトルからわかるように、これは、カンディンスキーを参照しつつ、微小重力環境において「上昇する六つの円」を等身大の紙に描くというものである。六つの円を六人の宇宙飛行士に見立て、「水平線」の解釈や、垂直/水平・上/下などの基本的な空間認識、さらに「上昇する」といった運動感覚がどのように変容し、それが空間表象にどのように反映されるのかを探ることが目的だった。合わせて、円を描く、線を引く、紙を破るといった基本動作が宇宙空間でこうむる変化も検証の視野に入れていた。
周知のように、衛星スパルタンを船外活動で回収するという急務のために放映はされなかったが、帰還後のインタヴューで、土井飛行士はミッドデッキで3時間も集中して一人で絵を描いていたことが明らかになった。しかしながら、作業空間の制約から紙をつなげて大きくすることはできず、レターサイズの用紙1枚にそのまま描かれた。身体を固定しない不安定な状態での描画作業だったが、食事用トレイをマジックテープでひざに付け、それを画板がわりにしたという。私たちは、作業上の制約条件をつかみきれていなかったのだ。
残念ながら、小さいサイズでは画面の軸性が意識によって容易に規定され、微小重力による上下の混乱や空間感覚の変化などの身体感覚レベルの変化は描かれた画面からは読み取れない。本来のインストラクション通り、身体を包み込む大きい画面に描いていたら、意識による空間規定は抑制されて、身体的な感覚の変化がより直截に現われてきただろう。また、制作中に他の宇宙飛行士とのコミュニケーションも生じたはずである。「何を描いているのか?」といったやりとりは、できあがる絵のあり方にも作用しただろう。作品形成をコミュニケイティヴな場の相互作用の中に差し戻すことが宇宙では重要になるのではないか、と私たちは考えたのだ。例えば、土井氏が描いた六つの円にそれぞれ飛行士を当てはめてみれば、軌道上を周回するシャトル内の空間イメージが新たなリアリティをもって立ち上がってくる(図参照)。これらの点は報告書の中でアニメーションを付けて分析している。
当の絵は、昨秋、土井飛行士自身から本学に寄贈されたので、今後じかに見ていただくことが可能になった。じつは私たち自身が実物を見たのはそのときが初めてで、それまでは貴重な資料ということでカラーコピーしか見せてもらえなかった。驚いたのは、予想以上に丁寧に塗られたクレヨンのタッチと色合いだった。もう1枚の絵には、シャトルの窓からみた尾翼の光景が同じくクレヨンで丁寧にスケッチされていた。土井氏によれば、一定の時間を費やして絵を描く行為は、写真や映像を撮るのとはちがった充実感が得られるという。自己集中を伴う表現活動が精神の安定化に大きく役立つことは、宇宙でも同じである。のちにコーヒーで即興的な宇宙書道を行なった若田飛行士も、微小重力環境下ではいくら筆に液体を含ませても垂れないので、長い一筆書きが楽しめると語っていた。
微小重力下では紙などの固定や身体姿勢に特別の工夫が必要だが、宇宙の特殊な条件を直接反映した絵画や造形は、それなりに新たな価値を持ちうるし、軸性を持たない丸い画用紙や特製の画材、制作プログラムを開発することは、宇宙での長期滞在になんらかの貢献を果たすだろう。何よりそれは、地上の造形行為を相対化する視点をもたらしてくれるかもしれないのだ。
生命の場所:宇宙飛行士インタビューから
芸術はつねに人間の生と死の問題に関わってきた。芸術の機能が、たえず新鮮な角度からこの世を知覚し直す方法を提示することだとすれば、あらゆる生命を育んだ地球を外から眺める視点をもたらす宇宙の体験は、それ自体ひとつの芸術的体験であるといえる。そうした体験を経た宇宙飛行士との対話は、具体的な芸術実験のヒントになるだけでなく、生命と芸術の本質的関係について深い思索を促してくれた。次に、都合7回に及ぶ宇宙飛行士インタヴューの中から、芸術に関わるいくつかの示唆的発言を抜きだしてみたい。
毛利飛行士は、死と隣り合わせで行動する個としての直観の重要性を強調し、次のように語った。
毛利:我々は訓練を通して、いつも余裕なく最終的にはギリギリのところで行動します。瞬間的に危機に陥ってどうしようもなくなったときに、習慣的に何を犠牲にするのか、プライオリティ、とまず考えるんですね。宇宙飛行士を見ていると、そのプライオリティを決めるときに、その人の能力が最大限発揮できる部分でやった方がいいわけです。それからセンサーについても、組織でマニュアルに従っていればいいところはあまり考える必要がありませんが、死ぬか生きるか、個人の判断が最終的に瞬間的に問われるときには、自分のセンサーが一番鋭い部分で判断するのがいいわけです。それは芸術の人もそうだと思います。自分の仕事を一番よくするためには、このミッション、このプロジェクトが、自分にとって何のためにあるのかということをはっきりさせることが大事です。
私はなぜここにいて、この仕事をしているのか――この問いをつねに自分自身に投げ掛けること、それは死の淵から生を見据えることにつながるだろう。これは芸術に関わる者の根本的覚悟として要請されているのではないか。
また、宇宙の「黒さ」と太陽の「白さ」についての次の発言は、大気と共に地上を包む光の神秘をあらためて示唆する。
毛利:先ほど光がない状態が宇宙の暗黒だと言いました。最初に太陽を見たときに、ああ、聖書に「初めに光あり」と書かれていたのはこのことなんだな、というのがわかったんです。暗黒の何もない状態で、太陽は真っ白なんです。色が何にもないんです。真っ白と暗黒。その暗黒というのが、ビロードのようだと表現する人もいたでしょうけれども、反射のない黒と考えてもいいと思うんです。僕が一番それが似ているというのは、暗闇で煤を見た感じ。(…)星を見ると、いろいろな色の星があるんですね。それは地上で見るのと同じなんです。そうしたときに太陽の白い色を見てもぜんぜん和まない。地上で太陽を見たら、まぶしいけれども、何となくああ暖かいという感じがしますけれども、宇宙で見た太陽というのは、自分の身体は熱くなりますけど、まったく和まない。
そして、毛利氏は、宇宙から地球を見ているときに、人間が「美しい」と感じる感覚が、地球上の生命の根本的ベクトルに根ざしている、という直観を得たという。
毛利:要するに、生命の流れの必然性、なんですね。今のところ、宇宙の歴史がおおざっぱに200億光年、(…)太陽が生まれたのが46億年前で、核融合反応でエネルギーが出て、塵とかそういうのが集まって、太陽が非常に大きいから、重力でもってその他の惑星もつかまった。隕石どうしがぶつかって中に入った水が、最初は熱い水蒸気だったものが温度が下がって海になって、その海の中から、太陽系が6億年ほど経つくらいに、生命というか有機化合物が生まれた。果たして偶然雷か何かで、二酸化炭素とアンモニアとかが結合してそういうものができたのかもしれませんし、あるいはまたハレー彗星みたいな彗星に乗っかって、有機物が飛んできたのかもしれません。とにかく生命ができて、その遺伝子、つまり自己複製できる有機物が連綿と今までつながってきたということ。このあたりは科学者としての知識ですね(…)。
自分自身はもともと核融合とか材料科学をやっていて、あまりこちらの方面には興味はなかったんです。それが、自分を変えたものは何だろう、美しく見ているのは何だろうと考えているうちに、ああこの延長線上にあるんだなとわかったんですね。つまり、地球という空間の中に自分を複製して綿々と生き延びてきた生命、それが多様化して現在ある人間というものが生まれて、続いてきているわけです。ということは、きっと続けていくという方向性があるんですね。時間と空間に対して、生命というものがずっと続いていく。その方向性を示すものが、ベクトル的に合っていれば、美しいと感じたり、逆に生命を滅亡させる、あるいは何というか、遮断する方向のものは嫌だという感覚が出てくるんじゃないか、と思うんですね。
福嶋:総合的に考えると、宇宙と全体が必然性の中に存在していることと、毛利さん自身を含めて人間が生命を維持していることが、まったく同等に必然性があるから美しいという意味ですね。
毛利:自分の存在を「肯定する」ということです。「肯定する」ということが美しいということを意識させる。それはきっと、例えば、青い色が美しいというのは、最終的に我々が生きているかどうか、息をしているかどうか、酸素を吸っているかどうかに関わるんですよね。酸素の色ですね、青の色は。
野村:液体酸素の色ですね。
毛利:そうですね。水の色も青いですし、光のスペクトルが目にこう来ますね。ところが、宇宙で見た太陽は、たしかに真っ白なんです。(…)先ほどの質問と関連しますが、青く見えたり、夕焼けが赤く見えたりするのが美しいというのも、宇宙から直接来る光、その中には紫外線や太陽から出ている高エネルギーの粒子とか、いろいろあるわけですけど、それらを全部カットしてくれる空気を通して見るような光だから、和むんじゃないか。そのもとで初めて生命が生まれ、進化して、多様化してこれたような。だから結論的には、生命を生かしてくれる方向にあるものが美しく見える。芸術もきっとそうなんじゃないかと思うんです。
この言葉は、科学と哲学と芸術が合流すべき場所を指さしている。そこは「生命の場所」である。これはおそらく芸術に関わるすべての人間が直観していることではないか。私たちの知覚の中に地球と生命の全歴史が織り込まれているのだ。だが、この歴史が奇跡的な偶然の相互作用で織り合わさっていることは忘れられがちである。私たちが日常的習慣の中で忘却している私たち自身の奇跡的な存在が、宇宙からの視点によって照らし出される。生命的自然の存在しない宇宙環境が特異なのではなく、生命に満ちた地球環境が宇宙の中できわめて特異なのだ。
向井千秋飛行士は次のように語る。
向井:この地球ってすごい特殊な場所なんです。多くの人がここに住んでいるから、みんなこの生活が当り前だと思っているけれども、多くの宇宙から考えたら、地球って特殊環境です。ほとんどの宇宙はこんなすごい環境ではないわけですよ。
(…)私が一番面白かったのは、宇宙飛行自体より、宇宙から帰ってきてここで起こっている特殊なことを見たことの方なんですよ。なぜかというと、自分が期待せずに帰ってきているから。宇宙で物が浮かぶとか、宇宙から地球がきれいに見えるというのは、期待して行ってるから、それは面白くても、自分の期待度がこのくらいだと、その差分というのが小さければ、うわー驚いた、とならないんですね。ところが、こういう当り前だと思っていた世界、不思議じゃないと思って帰ってきたところに、ものすごい重力がある。物がこういうところに置いてあるのも不思議、物がものすごい速さで落ちるのも不思議。そういうのを見たときに、そういうことに自分が驚くと思って帰ってきてないから、その驚きは、本当にびっくり。えーこんなすごい特殊なところだったんだ、と。
当たり前のものが当たり前でなくなり、あらゆる存在が目もくらむ多様性と特殊性の中に散開するこの知覚の転換は、芸術にとって本質的に重要なものではないだろうか。習慣という重力で固く縛りつけられていた存在が、無重力の中で固定的関係をほどかれ、世界が無数の驚異の織物になる。いわば現象学的エポケーが自然と遂行されるのだ。地球と生命自身がきわめて特殊でかけがえのないものであるという意識は、人類がこれから共有していかねばならないものでもあるだろう。
非人間的環境である宇宙はまた、人間の知覚の根底で作用している志向性を浮き彫りにする。毛利飛行士の言葉にもあったように、その志向性とは、私たち自身がその一部である生命への共感・共振である。ロシアの宇宙船の中にまぎれこんだゴキブリが宇宙飛行士たちにたいへん愛玩されたというのは有名な話だが、向井飛行士も、宇宙で生物実験をした経験から、人間が決して見飽きない対象とは、自分と同じ生命あるものだと述べる。
向井:今のところ(個人で)宇宙に持って行ける物は三点なんですよ。三点っていうと、だいたい自分の家族の写真なり、子供の学校のペナントとかを持って行ってるんですけど、私は、その中の一点を、自分でカセットの外側の箱の中にカイワレの種を入れて、うしろにベルクロテープつけて、宇宙で水を入れて水栽培。一つは、カイワレが出るかどうかに興味があったんですが、同時に、それを船内の壁につけて緑を宇宙で見ると面白いと思って持って行ったんです。それは自分が植物を好きなせいもあるけれど、あのような殺伐とした機械に囲まれたところに、こんな小さいカセットだけど、その中にカイワレが入っているのを見ると、やっぱりすごく心が休まりましたよ。
(中略)例えばメダカの実験だって、自分と同じ生命を持っている者どうしの親近感がものすごく出てくるから、非常に観察が楽しいんですよ。私たち、二回目の飛行でガマアンコウっていう醜い魚を持って行ったんです。宇宙飛行士はみんな地上で訓練するときにガマアンコウの泳ぎを観察することをトレーニングでやっていたけれど、軌道上に持って行くと、みんなそれを見るのが逆に楽しいんですよ。蓋が閉まっていて、一定の時間しか開けられないんです。魚の実験の邪魔になちゃうから。そうすると、みんな開ける時間になると「じゃあみんな、見よう」って、ペットを飼っているみたいな感じですね。
宇宙に長期滞在する宇宙飛行士にとって、植物や動物は目的に縛られた実験対象である以前に、目的なしに「見る」対象である。対象の識別や判定以前の、生命的コミュニケーションの一つの形としての「見ること/見られること」。そこで働いているメカニズムは何か。
井上:医学的に言って、人間が生物を見ていて飽きないというのは、どういうところから来ているのでしょうか。
向井:あれは、やっぱり予想ができないからじゃないですか。例えばおもちゃの金魚なんかは、どう泳ぐかがわかるじゃないですか。だけど生き物っていうのは、動きとかそういうものが予想できない部分と、慣れてくれば、とんとんと叩くとこちらに来るとか、予想できる部分がある。つまり、いわゆるフィードバックがある。自分のやったことに対して向こうが応える、そういう双方向の会話が成り立つから面白いんじゃないですか。植物もそうですね。水をあげると育つ。
井上:自分もそう考えていたので、ものすごくうれしい意見ですね。でも、生き物は最終的にすべてをコントロールできないっていうか、どうなるかわからないところがあるんですよね。
向井:そうそう。
井上:その辺の楽しみっていうのは、他の宇宙飛行士も同じでしょうか。
向井:同じだと思います。
井上:ということは、そこが普遍的なものなんだ。
向井:やっぱり双方向でフィードバックがある。こっちが構うと向こうが逃げる、だから追いかける、っていうのが面白いんですよ。
他なるものと共振しつつ、予測不可能なものに向って開かれているということ、それが生命の本質だろう。私たちの眼と心を捉えて離さないのもそれなのだ。このことは、作品や創作のあり方にとってもきわめて重要なことではないか。たえざるインタラクションとフィードバックを繰り返しながらも、あらかじめ予期された結果に向う運動ではないからこそ、芸術活動は無限に私たちを巻き込むのだ。そしてすぐれた作品は、たえずそうしたみずみずしいあり方を私たちに提示する。芸術とは本質的には予測不可能なものに向って開かれた生命が生命自身をなぞらえる運動であるかもしれない。
おそらく宇宙空間でむき出しになるのは、私たち自身と地球のあり方そのものなのだろう。「宇宙時代」の芸術は、生命的感性と惑星的想像力をベースにする。芸術もまた生命と同様、別のかたちに進化してよい。宇宙飛行士との対話、そしてAASでの研究は、さまざまな地上的現世的制約にもかかわらず、そんな直観を示唆してくれる得がたい時間でもあった。
井上明彦(造形計画)
