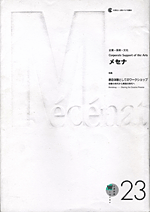*初出『季刊メセナ』第23号(社団法人企業メセナ協議会発行、1996年冬、pp.18-21)
ワークショップとは何のことか? ―アートの原風景へ—
ワークショップとは何だろうか。それは、パブリック・アートとかアーティスト・イン・レジデンス、あるいはミュージアム・エデュケーションといった、ここ数年とみによく耳にするアート周辺の新たな外来語のひとつ、芸術システムの「先進国」たる欧米から「後進国」たるこの国にまたもや移植されたアートと社会の関係の調整システムの一種だろうか。それは、一般参加者を喜ばせる新奇な体験型啓蒙教育だろうか。あるいは、アーティストが通常行なう作品制作を一般参加型に水増し応用したものにすぎないのだろうか。そしてぼくらは、百年以上前に「ビジュツ」という聞きなれない言葉に戸惑いながら、「展覧会」のために「術(アート)」があると観念してしまった先人の作り手たちのように、よく内容が飲み込めないまま、今度は展覧会場からアーティスト・イン・レジデンスやパブリック・アートの現場に出むくのだろうか。今、本当に問われているのは、アートと社会の関係を欧米流に調整することでも、アートと生活の溝を埋めることでもなく、アートそのものの近代的論理であり、ぼくたち自身の世界への住まい方をふまえながら、オルタナティヴな様態の中にアートの機能を解放することであるというのに。
ぼくは、いわゆるワークショップがもつ教育的・啓蒙主義的側面には否定的だ。 アーティストないしエデュケイターと市民のあいだに、施す側と施される側という区別が残っているとき、 施す側の方は何も変わらない。自己発見を通じて変わらなければならないのは、市民の側よりもむしろ、 アートとアーティストの側なのだ。が、ここではとりあえず、ワークショップの定義づけはいったん脇に置き、 他者の参加へと開かれた形成プロセスをもつ造形活動――ぼくはそれを「ワークショップ」というより、 「プロジェクト」と呼びたいのだが――の意義と可能性について、乏しいながら自分自身の経験に即して述べておくことにしたい。
昨年(1995年)の夏、岡山市の御野小学校が創立百周年を記念して、「アートワークみの」という現代美術展を開催した。岡山市に住む友人の画家が同校のPTA会長を務めていたために実現した催しで、ぼくを含めて20人近くの美術家が岡山内外の各地から出品した。その催しに参加を依頼されたとき、主催者から「作品の出品にしますか、ワークショップにしますか」と聞かれた。ぼくは、以下の3つの理由から、現場での集団制作を選んだ。第一に、小学生にとっては作品を見るだけの美術体験は面白くない(少なくとも小学生時代のぼくはそうだった)。第二に、生きている小学校を外から持ち込んだ作品の単なる展覧会場にしてはいけない。第三に、絵画であれインスタレーションであれ、作品を展示空間で見せる/見せられるだけの近代的な「美術」の仕組みに、このところ深い疑念と倦怠を感じている。
ちなみに三番目にあげた理由は、次のような基本的な問いと背中合わせになっている。なぜ、またいつまで、「美術」の生産と受容は、「展覧会」によって条件づけられねばならないのか。「展覧会」ぬきに「美術」は直接存在しえないとすれば(これは「美術」の定義上、歴史的に規定されている)、「美術」が「美術」であることをやめてなお、「術(アート)」でありうる可能性は何か。それはどのようにほかの「術(アート)」とつながれるか。

中原浩大《夢の中でこのかたちを完成しなさい》、アートワークみの
岡山市御野小学校、1995
こんなふうにぼくは、「展覧会美術」から距離をとるために子供たちとの共同制作を選んだのだが、それは「ワークショップ」と呼ばれるカテゴリーに分類されるものだった。ところが、実際に現地に行ってみると、できあがった作品を展示するものより、現場制作のもの、「ワークショップ」と呼ばれてもおかしくないものが多かった。特に興味深かったのは、他者の参加が不可欠な制作プロセスを持っていて、「作品」なのか「ワークショップ」なのか区別できないものだった。
例えば、中原浩大の《夢の中でこのかたちを完成しなさい》は、八百人におよぶ全校の生徒の机ひとつひとつに、作者が半分だけ描いた絵を置いて、あとは児童がそれぞれで自由に完成させるというものだった。大量の未完の絵はどれひとつとして同じものがなく、子供たちの創造意欲をかきたてる最低限のインストラクションが付されて、すべての教室の机を覆っている。ぼくは(そして作者自身も)見ることができなかったが、夏休みが終わって登校してきた小学生たちの反応ぶりもすごかったと聞く。中原は、自分は内向的な性格なのでワークショップの形式はとれなかったと言っていたが、自己の思考の核を保持しつつ、こうした開かれたプロセスへと表現を解放するかぎりにおいて、「作品」と「ワークショップ」の区別はすでに無意味だろう。
ぼく自身は、創立百周年ということから、百人の小学生たちといっしょに体育館全体を使って、「百年の空(そら)」というプロジェクトを行なった。まずひとりひとりが、御野小学校の創立された1895年から百年分の年号をそれぞれ選び、その年の空を自由な想像で縦2.5m×横1.2mの大きな布いっぱいに描く。絵の下には年号を書き入れ、それら百枚の空の絵を順に縫いつなげて、全長60mの長大な布の筒を作る。絵の裏面が内壁となるタイムトンネルの中は、布ごしにさし込むランダムな光と色が不思議な空間を作りだし、足元に年号の数字が並ぶというわけだ。子供たちの描く空の多様性が無限に変化する空の表情を示唆し、御野小学校がくぐり抜けてきたこの百年間の地上の変化に空から想いをはせようというコンセプトだが、当然ながら、できあがりはもちろん、できあがるかどうかさえ予測のつかないプロジェクトだった。

井上明彦《百年の空》、アートワークみの、岡山市御野小学校、1995
いうまでもなく、何より大事なのは、コンセプトや仕上がりよりも、この予測不可能なプロセスであり、その中で、構想したぼく自身も含めて、関わった人間が何を発見し、どう変わるかである。この点は、個人的な作品制作の場合と大差ないのだ。実をいえば、プロジェクトの構想も、小学校の校庭で空を見上げていた自分のことを思い出すことから出発したのだったし、小学生への美術教育的サービスなど考えてはいないのだ。すさまじい自己集中と奔放さを示す彼らはむしろぼくのライバルであり、作業はあくまで子供時代のぼくに向けられていたのである。
案の定、子供たちは、特大の布に面喰らう親や教師たちの心配をよそに、最小限の筆使いのアドバイスだけで大画面に飛び込み、1時間足らずで思い思いの空を描き上げてしまう。どれひとつ似たもののない青空、雲、夕焼け、星空、稲妻、キノコ雲…。面白かったのは、親や教師たちの反応だ。はじめ遠巻きに見ていた彼らは、布を縫い上げる作業量の膨大さにしだいに心配になって、家庭科室から数台のミシンを体育館に運び込み、にわか縫製工場をしつらえてしまった。蒸し暑い体育館を埋め尽くす布の海の中で、終日ミシンに向かいながら懸命に手伝ってくれたある母親が、次のようにつぶやいた言葉が印象に残っている。「自分にこんなパワーがあるなんて知らなかった、この力をふだんから発揮できればすごいわね」。
芸術を指すドイツ語の"Kunst"が、「わたしにできる」という助動詞と関連していることを想起しよう。ふだん隠されているこうした深い自己との接触こそ、ある意味でアートのアルファでありオメガであるかもしれない。それを促すのは、ある困難さを伴う身体的活動であり、目や手や耳に潜む諸能力の行使である。それらは総体として自己と世界の関係を変える力として働く。それは文字どおり「働き」であり、外的な目的ではなく自己自身に向かう「労働 work」である。作業全体のアノニマスで予測不可能な進行のなかで、複数の他者が異質な自己と世界の発見を繰り返す楽しく困難な「労働」、ぼくはそれを導くのではなく、後押ししつつ、いつのまにか限りない多様性と共にある自己を発見するのだ。

《OFF THE FLOOR》、自由工場、岡山市、1994
同じタイプの「労働」は、かつて自由工場で行なった“OFF THE FLOOR”という集団的プロジェクトにも見い出せた。
自由工場というのは、岡山市内にある解体予定のテナントビルの空きスペースをビルのオーナーから無料で提供してもらい、オルタナティヴなアートスペースとして、1995年春まで一年半近く自主運営したものである。ぼくたち美術家、建築家、音楽・演劇・映画関係者と一般の市民や学生が対等な立場で「工員」となって、現場制作やコンサート、シアター、交流会等を続けた自由工場は、それ自体、ビルオーナー服部恒雄氏の真のメセナによって可能となった長期のワークショップだったともいえる。アートの領域でぼくが考えていたのは、ビルを単なる展示空間にするのではなく、壊される運命にあるビルそのものから素材やコンセプトを引きだし、今の時代に生きることのリアリティーに重ねて表現することだった。
“OFF THE FLOOR”は、そのビルの6階フロア全面に貼られたPタイルをはがして、23年前のビル誕生当時の空間を再現するプロジェクトで、画家や彫刻家から公務員、議員秘書、高校生や大学生を含む約50人が参加してくれた。はじめにビルがオープンした1971年当時の自分についてひとりひとり語ってもらい、リラックスしたところで床タイル一枚一枚にナンバリングしてもらう。全員がフロアの随所にちらばり、床にかがみこんで黙々とタイルに番号を記入していくその光景は、これまでの美術で体験したことのない不条理な緊張とユーモアに満ちたものだった。その後に続く実際の床はがし作業が、どれほど多様な発見と自己集中、工夫やコラボレーションを誘発したかはいうまでもないだろう。タイルの傷みや変色は、過去にその上で行なわれた仕事のありようを想起させ、次々と現われては消える黒い床と黄色いタイルのパターンは、動く抽象絵画のようだった。
この肉体労働の締めくくりとして、ある主婦が出したアイデアは、アーティスト顔負けの痛快なものだった。ぼくらは、ビルオープンの記事の載った23年前の古新聞を図書館でコピーして用意していたのだが、彼女はその新聞の「今日の献立」欄の料理をそっくり再現することを提案したのだ。今思えば、その「コンニャクと豚のいり煮」こそ、最高のアートだったかもしれない。
だが、これまで述べてきた事柄は、決して新しいものではない。自分のなかの他者と他者のなかの自分が出会う創造的労働の契機(他者とは人間だけをいうのではない)は、これまでの実験的な芸術実践のなかに無数に散らばっている。問題は、それらの契機をアートの内から外へいかにして解き放つかということだ。そのことの必要性を誰よりもよく知っているのは、美術界の専門家だけを相手にする姿勢を捨てて、こうした労働に自分の生を賭けているアーティスト自身のはずである。
井上明彦