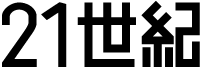 vol.5
vol.5
| モダニズム研究会会報 |
|
| 《投稿》 | ||
| 村田 靖子 | ---- | 忘却のすすめ――イスラエルで想うこと |
| 長畑 明利 | ---- | 「読者の死」――ミンチン・マー氏に聞く |
| 《海外出張報告》 | ||
| 稲賀 繁美 | ---- | エジプト調査の報告 |
| 《研究会発表報告》 | ||
| 野坂 政司 | ---- | デジタル・スペースと身体:巨人の肩車から見える世界と手触り |
| 長畑 明利 | ---- | 他者に成り代わる試み―アラキ・ヤスサダの実験 |
| 澤 正宏 | ---- | 理念としての戦後―戦後詩 |
| 《パネル・ディスカッション》 | ||
| 小畑 精和 | ---- | ナショナリズムとキッチュ |
| 加藤 光也 | ---- | シェイマス・ヒーニーからポール・マルドゥーンまで |
| 鈴木 将久 | ---- | 日中戦争期の中国モダニズム−香港の位置をめぐって |
| 高橋 世織 | ---- | フレーム体験について |
| 《研究会発表報告》 | ||
| 稲賀 繁美 | ---- | 岡倉天心とインド--越境する近代国民意識と汎アジア・イデオロギーの帰趨 |
| 《講演要旨》 | <||
| 崎山 政毅 | ---- | メキシコのユリシーズ |
| 港 千尋 | ---- | ワールブルグの《記憶の女神》 |
| 《出版プロジェクト》 | ||
| 西 成彦 | ---- | 第1章 20世紀における表現とディアスポラ状況 |
| 三宅 昭良 | ---- | 第2章 越境と文化アイデンティティー――あるいは〈越境〉とは何か |
| 和田 忠彦 | ---- | 第3章 権力と記憶 |
| 大平 具彦 | ---- | 第4章 モダニズム/アヴァンギャルド表現の再検証:概要とコメント |
| 高橋 世織 | ---- | 第5章 表象からの越境 |
|
《投稿》 忘却のすすめ――イスラエルで想うこと村田 靖子 この夏もまた2カ月、イスラエルですごした。 イスラエルではよくこんな風に言う。「エルサレムでは祈り、テル・アヴィヴでは踊り、ハイファでは働く」と。三つの一神教が聖地とみなすエルサレムには、世界中から巡礼がくるし、住みつく信者も多く、町中が祈りに満ち満ちて空気は異様な熱気をおび、重苦しい。テル・アヴィヴは地中海的な享楽の雰囲気と商業主義の町。そして、イスラエルで三番目に大きい都市ハイファは、港町として、工業都市として、そして今ではハイテク産業の中心地として重要な都市になっている。今年の夏はおもにハイファの大学にいた。 日本を発つ直前、パレスチナ人作家ガッサン・カナファーニの短編をいくつか読んだ。そのうちの一つが「ハイファに戻って」で、この秀逸な作品からうけた深い感動の余韻を味わいながらわたしはハイファに着いた。 物語のあらすじはこうだ。1948年のイスラエル独立戦争勃発の混乱期に、ハイファに住むアラブ人夫婦は生まれたばかりの赤ん坊をやむなく家に残したまま、難民となってハイファを離れ、西岸地区のラッマーラに暮らしていた。六日戦争後、20年ぶりに故郷訪問を許され、おそるおそるハイファの元の自分たちの家を訪れる。そこにはホロコーストを生き延びイスラエルに移住してきたユダヤ人夫婦が暮らし、残していった息子はその夫婦の息子として、つまりユダヤ人として成長し、いまやアラブ人と戦う青年となっていた。 歴史が残酷に運命を狂わせる。人間悲劇の普遍的な現実をつきつけられ、沈鬱な重い痛みが読者の心に沈殿する。完成度の高い作品である。カナファーニの作品はどれも深い人間の真実を描き、しかもその眼は同胞のパレスチナ人たちへも容赦なくむけられる。 わたしはこのカナファーニの作品からうけた激しい衝撃を、そのままハイファまで引きずっていった。ハイファはアラブ人の町だった。重要性からいうと、そこから北にバスで約一時間のアッコのほうがはるかにまさる。アッコはすでに紀元前19世紀にはエジプトの文書にその名前が出てくるほど古くから栄えた町だ。それにくらべ、ハイファが重要になったのは、ダマスカスまでの鉄道が敷かれた20世紀初頭のことで、そのころからシオニズムの波にのって移住してきたユダヤ人の数もしだいに増えはじめた。 カナファーニの作品の舞台になった海に近い下町にあるアラブ人地区を歩きながら、1948年の混乱を想像した。その後ユダヤ人やキリスト教徒が住みついたところも、わたしの目をひく建物はアーチ式の入り口や窓をもったアラブ風の建物ばかりだ。暴力的に家を、祖国を奪われ、難民となって生きること。ハイファ大学で出会った、アメリカ国籍をもち、アメリカに住む、超インテリのパレスチナ人女性が「わたしは難民よ」といったとき、頭のなかでいろいろなことが錯綜して、どう会話をつづけたものか一瞬ためらったときのわたし。さまざまなことを考えながら、カルメル山の上にあるユダヤ人たちの整然とした美しい住宅街でなく、中近東独特の喧噪と無秩序が充満するハイファの下の町を歩いた。 そのとき、わたしはエリ・ヴィーゼルの『死者の歌』を思い出した。現在はルーマニアの一部になっているトランシルヴェニアのシゲトという故郷の村を、エリ・ヴィーゼルはビュッヒェンヴァルトで生き延び、解放されてから20年たって、はじめて訪れ、かつて自分の家だった建物を眺めた。これも暴力的に家と故郷を奪われた者の帰郷の記録。もうひとつ、去年東京で開かれたイスラエル・ドキュメンタリー映画祭で観た『エルサレムの家』という記録映画を思い出した。難民となってやむなく東エルサレムに移ったアラブ人は、西エルサレムの家をユダヤ人に奪われた。そのアラブ人がかつて自分のものだった家を見に行く。アモス・ギタイというイスラエル人監督の作品だった。 バビロン捕囚の身となったユダヤ人はバビロンの流れの畔でシオンを想って涙した。その後故国にもどり、神殿も再建したが、ふたたびローマ帝国のエルサレム神殿破壊によって敗北したユダヤ人は、離散の民となった。離散の悲運のなかでユダヤ教は確立していったが、つねにシオンを懐かしみ、「来年はエルサレムで」の合い言葉を世界中で交わしてきたユダヤ人。ところが、イスラエル建国によってユダヤ人が国をもつようになって、こんどはそこから難民となって追われたパレスチナ人が、それまでのユダヤ人と同じようにパレスチナ(シオン)への帰還を熱望する事態が生まれた。パレスチナ人の「シオニズム」はユダヤ人のシオニズムと瓜二つで、それもまた「記憶」を武器に、失われた土地を奪還する夢を抱きつつ、離散の悲しみのうちにますますエネルギーを増幅させる。 数年前、テル・アヴィヴ大学教授のユダヤ人が、新聞に〈忘却の必要性〉という題の文を載せ、国中から囂々たる非難を浴びたという。ホロコーストを「記憶の政治学」のなかで利用するな、記憶をおしつけて子供たちにトラウマを植えつけるのはやめ、少々の「忘却」によって、癒しの方向へ進もうではないのか、といった主旨だ。 記憶がどす黒く渦巻くイスラエルのような国には、もしかしたら、この教授がいうように「忘却」を処方する必要があるのかもしれない。だが、3000年も前から記憶しつづけることを存在理由にしてきた人々のあいだで「忘却」を説くのは、サハラ砂漠に小さなジョーロで水をまくようなことかもしれない、とも思う。ふたつの民族の記憶と記憶がぶつかりあう。 「読者の死」――ミンチン・マー氏に聞く 長畑 利明 北京への出張の際に、アメリカを中心とした英語圏におけるアヴァンギャルド詩人たちに詳しいミンチン・マー(Ming-Qing Ma)氏のお話を聞く機会を得た。氏は中国生まれの新進の研究者で、スタンフォード大学で Ph.D を取得した後、現在は、ネヴァダ・ラスヴェガス大学で教鞭を執っている。『現代文学』(ContemporaryLiterature)をはじめとする各誌に、アメリカ、カナダの「言語詩人」についての優れた論考を精力的に発表しており、その一方で、言語とイメージに関する研究も進めておられる。 インタヴューは、第18回国際エズラ・パウンド学会のセッション終了後に、学会開催地である北京の北京外国語大学にて行われた。以下は英文のテクストを和訳したものである。 AN: 私はいま「モダニズム研究会」という研究グループに入って、「越境」をテーマに研究しています。私自身は特に「自己」と「他者」の越境というテーマに関心を抱いています。とりわけ興味を引かれているのが、英語圏の詩人や小説家たちの「他者の声を得る」ための様々な試みです。今世紀は他者の声を獲得するための様々な実験が為されてきたと思いますが、「言語詩」の試みもその中に入れて良いのではないかと考えています。単一の著者の声の真正さ(authenticity)に対する懐疑と、詩は言語という社会的歴史的諸関係のマトリクスによってできているという彼等の主張の背後には、自己と他者の越境に対する関心が反映されているのではないかということです。 このトピックと関連するのではないかと思うのですが、マーさんは今「詩におけるパフォーマティヴィティ?新しいミレニアムの〈詩論以後〉」というシンポジウムを企画しているとお聞きしました。そこで問題となるのは、「著者の死」と対照される「読者の死」というコンセプトだということですが、まずはこのコンセプトについて説明していただけますか。 MM: 「読者の死」に対しては何年か前から興味を持っています。1993年に、モダンとポストモダンの詩と詩論に関する卓越した批評家であるマージョリー・パーロフが、ポストモダニズムにおける「開かれてあることについての展望」(the prospects ofopenness)に関する論考を発表しました。この論考の中で、彼女はスティーヴ・マッキャフリー(Steve McCaffery)やローリー・アンダーソン(Lauri Anderson)といったアヴァンギャルドの詩人とパフォーマティヴ・アーティストについて論じているのですが、論考の最後で、彼女は一つの問いを投げかけています。それは、1990年代のさまざまな作品に適用されるものとして、「ポストモダニズム」という用語は適切なものだろうか、すなわち、私たちがまだそれに対する名前を得ていない芸術の一局面を、「私たちがまだはっきりとは概念化できていない」詩のあり方を、予測することが出来るのだろうか、それとも出来ないのだろうか、という問いでした。『ページの上の詩、外の詩』(Poetry on and off the Page)と題された評論集に収められた「自由詩のあとで」という最近の論考で、彼女は再びこの問題を論じており、1990年代後半に現れた「非線形的な詩」(post linear poetry)に対する名前を私たちがまだ得ていないことを繰り返し指摘しています。この文脈において、今世紀の終わりに近づいている私たちは、それ以後も、さらに緊急を要するいくつかの問いに直面しています。「21世紀に詩はどのようなものになるのか」、「私たちは21世紀の詩についての適切な概念あるいはアイディアを得ているのだろうか」、あるいは、「私たちにはそのような詩のための語彙を得ているのだろうか」といった問いです。それゆえ、新しい千年紀をまさに迎えようとしている今、未来の詩と詩のあり方を再概念化し、再び考えてみることが、極めて重要なことだと、私は考えるわけです。 今年のはじめに、私は勤務先の大学に対して、この問題に関する全国レベルの学会を開催するための計画案を提出しました。残念ながら予算を得ることは出来ませんでしたが、この埋め合わせをするため、私は同僚のスーザン・ヴァンダーボーグとともに、シカゴで開催される今年のMLA(近代言語協会)に、私が「ポスト詩学」(post poetics)と呼ぶものについてのシンポジウムを共同主催することにしました。シンポジウムの正しいタイトルは、「演じられるテクスト?新しい千年紀のポスト詩学に向けて」(Performed Text: Toward a Post-Poetics for the New Millennium)です。スーザンにとっても私にとっても、鍵となる考えは「パフォーマンス」あるいは「パフォーマティヴィティ」というもので、私自身のアプローチは、「パフォーマティヴィティ」を、私が「読者の死」と呼ぶものとの関連で強調するものです。 「読者の死」という私の考えは、ポストモダニズムに関する批評のいわばアキレス腱に対する批判です。たとえば、著者の死の強調は、意味の産出において読者が果たす重要な役割に対する強調に呼応しています。その結果、批評の実践における〈主体性〉あるいは〈主体の自律性〉の問題??これは従来〈著者〉の領域で疑問に付され、また脱構築されてきたのですが??この問題がそっくりそのまま、所与のものとして、〈読者〉の領域に場を移してきたのです。私がやろうとしていることは、このテクストと読者の関係についてのポストモダン的構築を批判的に再吟味することなのです。 「読者の死」の概念化において、私は「パフォーマティヴィティ」という用語を用いています。この言葉で私が言おうとしているのは、テクストというものは読者が演じる(パフォームする)ものだということではありません。ポストモダンの言説でも、読者は象徴界の法則によってあらかじめ定められた言語=表象パラダイムの中で、すでに形成されている解釈者のエイジェンシーという機能を、どういうわけか常に維持することが出来るとされています。これに対し、「パフォーマティヴィティ」が意味するのは、テクストそれ自身が読者を「パフォーム」するということで、この場合読者は、「テクストの外部に位置し、意味の(再)産出のプロセスにアクティヴに関与する意味産出者」であることをやめるのです。 というのは、非線形的な詩の多くが提示し、また実践しているのは、スティーヴ・マッキャフリーが「構築以前の前言語的な主体の状況」と呼ぶもの、つまり、一見すると意味の座標を伴わないように見える視覚的・聴覚的な配置を前面化することだからです。そのようなテクストでは、素材の物質性が「理解」というよりはむしろ、多元的で多方面に向かうような「配置」を要求するのです。たとえばプラスティックのページの使用によって可能になる、複雑で変化するタイポグラフィーやトポグラフィー上のさまざまな配置がそれを証明しています。ページの構成は、文字どおり、「物質的な動き」を繰り広げ、それがさらに、「読む進めること」(reading-on)ではなく、ましてや「読み通すこと」(reading-through)でもない、テクストの物質的渦巻き「とともに読むこと」(reading-with)をもたらすのです。そこに到達するためには、たとえば実際にページを繰り、本を動かさなければならないのです。この「ともに読むこと」において、読者はその〈動き〉の一部となります。読者はテクストの中の物質に還元されるのです。フランスの哲学者ミッシェル・セールが「言語の起源」というエッセイの中で述べたように、そのテクストにおいては、「存在論的に言って、読者は、水晶、植物、動物、あるいは世界の秩序と何ら区別されることがない」のです。 私が「パフォーマティヴィティ」という言葉で言おうとしているのはこういうことです。現段階では、これはまだ極めて純理論的であり、実験的なものであって、まだまだ注意深い思索と発展が必要ですが。 AN: 大変興味深いですね。最近10年ぐらいの間に起こっている新しい詩のあり方には私も興味があります。今話していただいた新しい動向に属する詩人の名前を挙げていただけますか。 MM: すぐに思い浮かぶのはカナダの「言語詩人」クリスチャン・ベク(Christian B嗅)です。彼の詩はこの点において実に革新的なものと考えられています。もちろん、スティーヴ・マッキャフリー(Steve McCaffery)をはじめとして、他にもこのカテゴリーに入れたい詩人はいます。 AN: そういった詩人たちは、基本的に創作家なんでしょうか。それとも、理論も書いているのでしょうか。彼らは自分たちがどのようなことをやっているのか説明しているのでしょうか。 MM: 実際に訊いてみれば、彼等は自分たちがやっていることを説明してくれるだろうし、多くの詩人たちが自分の理論を、というか、もう少し正確に言えば、文学批評を書こうとしているとは思います。しかし、一般的に言って、私は彼らの説明が、私たちが一般に使っている意味での「理論」であるとは考えていません。 AN: 声の真正さについてお聞きしたいのですが、これは、あるいは、真正なる主体性というものは、今日では、一般的に言って、懐疑の対象と見なされているのでしょうね。 MM: 一般論としてはその通りだと思います。声と主体性について話すとき、声も主体性も無垢なものではないということを思い出さなければならないわけです。ポスト構造主義の視点から見るときは特にそうです。どちらも構築物(constructs)なわけですね。ですから私も、それがどんな種類の声や主体性であっても、それらに対して極めて用心深い態度を取らなければならないと考えています。真正なる声や主体性(authentic voice or subjectivity)に対してはことにそう感じます。 AN: ベク、スカラピーノ(Leslie Scalapino)、マッキャフリーといった実験的な詩人たちの作品というのは、80年代、90年代、そしてもしかすると2000年代の実験詩ということになるのでしょうが、こうした詩人たちは、先ほど私が言った、自己と他者の境界の越境という問題に興味があるのでしょうか。多くの人たちが、主体と他者との間を架橋するということを言います。人種、性差、階級その他における境界を越えて、他者に手を伸ばすというわけです。今マーさんが名前を挙げた詩人たちも同様にこうした関心を共有しているのでしょうか。 MM: 人種であれ、性差であれ、階級であれ、「境界を越える」という考え方は新しいものではありません。たとえば、ジョン・アッシュベリーの詩では、人称代名詞が読み手を大変混乱させるように使われています。アッシュベリー自身、自分が「彼」(he)と言うとき、それは必ずしも「男性」の単数を指すとは限らないと言っています。こうしたアヴァンギャルドの詩人たちは、異なる媒体間の越境、異なる分野間の越境を含め、越境に関するあらゆる類の実験をしています。境界を越えることは、それだけですでに他者への参入を意味すると私も思います。しかし、「他者」の概念は、人種、性差、階級よりもさらに大きなパラメーターなのかもしれません。たとえば、主体が言語的に構築される以前の「物質的他者」(physical other)というものがあり得るのではないか、あるいは、そのような「物質的他者」とは何か、という問いに私たちは答えねばなりません。 AN: 「物質的他者」という考え方は面白いですね。ところで、英語圏の実験詩に関して、他にはどのような領域に興味がありますか。21世紀に重要となるかもしれない他の動向が現れてきているのでしょうか。 MM: 若い世代の詩人で「言語詩人」第二世代と呼ばれている人たちがいます。彼らは「言語詩」のプロジェクトを継続していると考えられているわけです。私はまだ彼らの作品をそれほど注意深く研究しているわけではありませんが、現時点での私の一般的印象を言えば、若い世代に大変将来性豊かな詩人が何人かいるが、彼らの作品は、私たちが話題にしている詩人たちに比肩できるような詩的洗練と批評的な鋭さをまだ見せてはいないということになります。彼らは今後偉大な詩人になるかもしれません。これは単なる私の個人的見解であって、間違っているかもしれませんが。 AN: マーさんは、革新的で興味深い詩人たちをずっと読んでこられたわけで、彼らについてのお話は大変啓発的で面白いと感じました。今日はどうもありがとうございました。 《海外出張報告》 エジプト調査の報告稲賀 繁美 「エジプトにおける近代化とオリエンタリズムの図像的研究」というような題目(正式書類が手元になく、不正確で済みません)で、西暦1999年12月25日(出国)より2000年1月8日(帰国)の調査をする機会を得た。以下その旅程と成果とをご報告申し上げる。 25日深夜にカイロ到着。目下カイロ大学日本語科で教鞭を取る鈴木貞美教授一家のお世話で、ナイル川中洲のザマーレクにある、ペンション・ザマーレクに到着。ここを基地とする。翌朝よりまず、エジプト考古学博物館の見学。 展示の政治学という見地から、ここ十数年にわたる同博物館の展示方針の変化を検討する。八十年代には、いわば西洋からの眼差しに晒されるオリエント世界という受け身の立場を当然としていた発掘品の羅列が、今回はポスト・コロニアル状況への自覚とその反応としての、ガイドの今まで以上の"タカリ"根性の昂進、また外国人観光客相手の展示美学の洗練(とりわけツタンカーメン関連展示品の、美術宝飾品としての展示姿勢、ミイラ室別料金という経営"改善"、中国製品中心のスーヴェニア・グッズ売り場の充実)が確認された。おりからの断食月もあり、公共施設は午後三時過ぎですべて閉鎖、特有の社会階層の事情もあって、博物館員との予約なしの面会は実現しなかった。ムハンマド・アリー・モスクの見学、ギゼーの遺跡管理局との接触も、こうした状況ゆえに果たせず、わずかに観光局の窓口の係員と接触を持ち、意見を交換するにとどまった。 27日にはコプト地区の重要な史跡を訪問。コプト美術館でも、おそらく断食月の影響か、館員との接触は不可能だった。とまれ、1983年当時と比較して、少数民族擁護政策の現れか、マル・キルギス教会ほか、美術館周辺の歴史的環境の再整備の進展を確認することを得た。特に1983年当時は線路に下車するだけの郊外電車が、今では立派に地下鉄となっていた。 28日には早朝空路ルクソールに飛び、19世紀西欧絵画におけるオリエント世界表象のありさまを現地において検証する機会を得た。ジャン=レオン_ジェロームが一八七三年のサロンに展示した《誘拐》(ナント)はルクソール神殿を背景として、アラブ時代の政治的な誘拐を物語り風に描くが、この作品の制作のために画家がエジプト旅行で踏破した地点をほぼ同定することができた。カルナック神殿では、午前中の見学と夜になっての光と音の演出を通して、歴史的・考古学的知識がいかに教育的なプログラムに組み入れられて現在用いられているかを検証した。アクナートンを世界最初の一神教の主導者として描く歴史解釈には、イスラーム国家としてのエジプトのおかれた位置と、西欧キリスト教国への配慮が伺われ、これを直接訳した日本語での解説に対する日本人観光客の反応からは、こうした演出と日本における高等学校などでの世界史教育との落差に由来すると思われる違和感が観察された。29日には王家の谷を見学した。その入り口にあたるナイル西岸では、多くの一九世紀オリエンタリスト画家に題材を提供したのみならず、早くは古代キリシアにおけるパウサニアスの旅行記から、近くはヘンリー・ミラーなどにいたる著述家の想像力を刺激してきたメムノンの巨像にまつわる記憶を検証した。今回の調査では、オリエンタリズムにおける観光人類学的な視点も考慮に入れたが、とりわけ王家の谷におけるガイドの説明には、対象とする客の国民性に合わせて、内容・文体に著しい対比の見られることが、改めて確認できた。 30日にはカイロに戻り、まずイスラーム美術館における、イスラーム展示の在り方を、歴史的変貌をも視野に入れつつ検討した。美術館という、いわばイスラームとは無縁の西欧近代の装置と、そのなかに無理やり取り込まれた異文化要素とのちぐはぐな混在の様子は、これまで体系的に文化交流における価値観の相克の問題として取り上げられることがなかった。だがペルシア、トルコ、インドさらには東南アジアから日本を含む東アジアにいたるまで、博物館という仕組みと、そこでの展示にまつわる政治学は、ポスト・コロジアル状況を喧伝される今日において、文化摩擦の浸透圧と化学変化、さらには放電現象の現場として、地球的な視野からの体系的な比較検討を求められていることが、改めて納得できた。同日の午後には、カイロ市街北部のエル・ハーキム・モスクを訪れた。ここは一九世紀三〇年代に、プロスペロ・マリヤが訪れて、いわばロマン主義的廃墟の美学というフィルターを通してオリエント世界を図像化した舞台であった。マリヤがグレコ・ローマンの廃墟趣味をエジプトに投影したことと同時に、カイロでもっとも古いイスラーム市街防衛の要でもあったフトゥーフ門を疎かにして、ひたすら牧歌的な解釈を加えていることも判明した。この日の夜には、こうした調査の中間報告を兼ねて、カイロの国際交流基金で英語での即興の講演--話題提供--をするとともに、現地の知識人と有益な意見交換をする機会を得た。深夜まで席を設けて下さった担当の遠藤、高橋両氏、および会合を企画された鈴木貞美教授、カイロ大学のムハマド・ファトヒ教授ほかの皆様に、この場を借りて、ひとこと篤く御礼申し上げたい。 31日は金曜日でイスラームの祝日がたまたま西暦では第二千年紀の最後の日と重なった。今までの強行軍がたたってやや風邪気味のため、調査活動は控えた。夜になって、ギゼーのピラミッドで、ムバラク大統領の肝入りで、イギリス統治下でのスエズ運河開通に合わせた歌劇アイーダ初演にも匹敵するアトラクションが挙行された。ジャイカの関係者が、テロへの心配から急遽欠席を命じられたため、入場券を譲り受けて会場に出向いた。だが、要人招待の警備に加え、公称五万人に昇る入場券購買観客の交通整理の混乱、さらには折からの濃霧発生もあり、結局現地の駐車場までたどり着いたところで、見学は諦めて帰路に着く。 西暦では二千年元旦。朝から濃霧が続き、予定していたシャルム・エル・シャイムへの移動は、航空機の状況が分からないまま放棄を余儀なくされる。このため、予定を変更してサッカラを訪問。世紀末にタヒチにわたったポール・ゴーギャンが携帯したいわばポータブル美術館の図像資料のなかにはサッカラの浮き彫りの写真が含まれていたことが知られている。そのオリジナルとの照合を果たす機会がこうして得られたのは幸いだった。ゴーギャンに端を発する二十世紀からの「始源主義Primitivisme」がそのイデオロギー的なより所を古代エジプトに求めたのは、決して偶然ではない。その精神史復元の鍵がここにあった。 翌日シャルム・エル・シャイムに、予定を一日遅れて到着。ここでの眼目は、長らくイスラエルによって前線基地として利用されていた土地が、エジプトへの返還後、いかに観光資源として再利用・開発されるに至ったか、という観光人類学および都市開発の検討にあった。おなじエジプト国内でありながら、西欧の主要リゾート経営企業が参入し、また地域によって、ドイツ、イタリア、フランス、ロシアなど顧客の国籍で色分けでき、もっぱらドルのみが通用し、バクーシを要求せず、しつこく品物を売り付けようとする商売根性や集り[たかり]とも無縁で、ラマダーン[断食月]とも断絶し、すっかり西欧的市民社会の流儀の責任意識を模倣した現代の租界。周囲のアラブ世界からは隔絶されたこの「別天地」では、ある意味で"殺菌"され、"西欧化"された人口都市の模造スークの実態をつぶさに観察することを得た。 4日にカイロに帰着。さっそく国立近代美術館、アート・センターを訪れる。前者では、改装中ゆえその全貌を掴むには至らなかったが、幸い館長との面会をその場で取り付けることができ、館の運営に関して質疑応答を得たほか、エジプト近代美術--日本ではまだ手付かず同然の分野--に関する刊行物の寄贈を受けた。アート・センターでは責任者は不在だったものの、現場で現代の創作家たちの展覧会を企画している責任者と意見を交換できた。夕刻には一橋大学で社会言語学の博士号を取得したアーデル・アミン氏の案内で、通称ファラオ美術館を訪問し、私立の主導によるエジプト文化・芸術紹介の企画のありかたを詳しく観察する機会を得た。科学的には多々問題のある企画でも、逆にその歴史的に拘束された観点(例えばアレクサンダー大王に対する、素朴な敬意の吐露)、エジプトにおける現在の労働コストの低さを物語る、実演つきのファラオ時代の生活の再現展示、また王家の谷とエジプト考古学博物館とに分離されて一括には復元できていないツタンカーメンの墓の原寸大の復元、さらにはイスラーム圏各地に風俗・文化に関する教育的配慮あふれた展示などは、国家主導の文化政策あるいはプロパガンダとは一線を画した、ある時代の展示イデオロギーを証しするものとして、博物館の系譜学、政治学という文脈のなかで、珍重に値するだろう。 5日には早朝から、年末に調査し損なったギゼーのピラミッド周辺の発掘の歴史的経緯と現在の観光政策を検証した。ピラミッドの周囲を利用した、膨大な質量の乗馬訓練所の存在が、今日にいたるイギリス植民地支配の痕跡として理解できた。 いわばこうした外国人旅行客や滞在者相手の廏舎のなりわいのなかに、ポスト・コロニアルといわれる現今の世界の経済的力関係が集約されている。出発以前には予期していなかった調査対象から、二十世紀初頭、イギリスの属国となっていたエジプトのモダニズムの実態に迫る鍵が得られた。 6日にはワディー・ナトゥルーン訪問。ナトリウム塩が噴き出た涸れ谷は、コプト教の修道院がかつて数多く点在した場所として、記憶されている。おりからコプト暦での主の誕生祭前日にあたっていて、残存する最大の修道院、聖マカリウスは訪れることができなかったが、ピショイ修道院、聖母修道院、それに西はずれの処女マリア修道院はつぶさに視察でき(あわせて、市販の案内所の誤謬も訂正することを得)た。観光客は普段訪れることも少ない、こうした辺境が、実は先進的な学問僧たちの努力でホーム・ペイジを開設し、世界との接触を積極的に図っている、といった実態には、なにか白昼夢を見ているような驚きがあった。 この日の夕食の宴には、鈴木邸にジャイカの大高夫妻をはじめとした関係者や、先に述べた、ファトヒ、アミン氏を始めとするエジプトの学者たちも招かれ、有意義な学術情報の交換がなされた。帰国日の7日の午前には、ザマーレクの近所に最近開館された陶磁器美術館を訪問。西欧の美術範疇では必ずしも美術作品とは認定されず、応用芸術として軽視されることの多かった作品に焦点を当てた、イスラーム文化展示の政治学を改めて反芻した。 最後に一言するならば、今回筆者が調査の拠点としたペンション・ザマーレクは、一橋大学の加藤博教授ほかが現地調査のたびに世話になっている宿であり、その宿泊者たちから得る情報は、鈴木家の運転手、サイード氏のそれと並んで、極めて貴重な証言となった。ラマダーン期間中の調査としては、著しく効率も良く、密度の高い調査が行えたことに関しては、鈴木教授はじめ、関係者に深く御礼申し上げる。なお本調査での知見、とりわけ19世紀西欧のオリエンタリズムの現場検証、エジプト近・現代美術の動向および現今の美術館行政の政治学に関しては、科学研究費による研究の一環として、今後順次発表してゆく予定である。 西暦2000年1月28日記 《研究会発表要旨》 1998年12月22日 野坂 政司 私たちの「動物と機械という両領域にまたがった身体」(ブルース・マズリッシュ『第四の境界:人間-機械[マン-マシン]進化論』、ジャスト・システム、1996、17頁)が技術的環境として直面している電脳社会の到来により、私たちの認識が形成されるときに辿る道筋は、その深層において、気づかぬうちにそれ以前とは異質のものに変容しているのではないだろうか。そして、私たちの認識の枠組みにつきまとうその不確定性の立ち現れは、デジタル・スペースの生成以前と以後により、身体性の場においてどのような差異を示しているのだろうか。 二人のウィリアム、ウィリアム・バロウズと、ウィリアム・ギブソンによる小説空間の差異は、このような疑問を解きほぐす議論のきっかけになるだろう。 ウィリアム・バロウズの言語実験としてのカットアップの手法は、書き手に固有の言葉の連続性を切断し、言語というシステムに亀裂を生じさせる実践であったが、彼の関心は、言語だけではなく、映像にも向けられていた。たとえば、『爆発した切符』(1967:邦訳、サンリオ、1979)の中の「見えない世代」には、「テープレコーダー」や「トーキー・フィルム」を使った映像と音声のカットアップの具体的な手続きを示しつつ、見えるものがきこえるものによって左右されてしまうという現象が詳述されている。言語におけるカットアップと同様に、映像と音声の組み合わせは編集・加工処理によって自らの当初の文脈から切断され、そのことが、それを知覚する者に心理的眩暈を引き起こさせることになる。バロウズは、60年代の電子技術の水準でどのような情報の編集と操作が可能であったかということを示しているわけであるが、今日、我々が、自らの日常生活において、音声や映像に出会う度にその背後の編集・加工過程の存在を常に意識することはないだろうし、また音声や映像を消費するだけの立場からはそれは不要なことだろう。しかし、単純な手仕事による60年代の編集作業でさえもバロウズが示唆したような視覚と聴覚の感覚の惑乱を引き起こせるのであるから、マルチ・メディアが喧伝される今日において、一定の意図に基づいて編集・加工処理を加えられた映像や音声は、広告の世界に代表されるように、見る者に対する映像の効果と影響の大小が存在理由のものさしとなる世界をさらに加速させる働きをする。 電子技術の発展によって、映像を見つめる人々の意識は、その映像によって示される被写体の自明性に対する懐疑を増幅させるだけではないだろう。ウィリアム・J・ミッチェルの『リコンフィギャード・アイ:デジタル画像による視覚文化の変容』(アスキー、1994)が明快に描き出した視覚文化の住人は、映像の仮想性と現実性との間に境界線を引けないような曖昧な性格と戯れる感覚や態度を自分のものとすることさえするだろう。ウィリアム・ギブソンの『ニューロマンサー』(早川、1986)が言語化している空想的電脳世界こそ、そのような方向を突き進んでいく果てに現れてくる、いわゆるヴァーチャル・リアリティーなのである。この作品では、コンピューターに関連する語彙が肉体や感覚を指示する語彙と結びつけれられて頻繁に使用され、作品の中のイメージは電子技術に基礎づけられた社会の描出へと方向づけられている。興味深いのは、電子技術と肉体の絡み合っているイメージ創造に貢献する表現である。アナログ的世界では、肉体に電子的道具が接合・内蔵されると、その電子的道具は肉体の機能の拡張として位置づけられるであろうが、このギブソンの空想的世界では、肉体は環境を把握していく基軸を成すものではなくなり、肉体は電脳スペースの端末と化してしまっている。このヴァーチャルな世界では、肉体は電子技術によって操作される対象として部品化されてしまうのである。 このような仮想的現実によって構造化された社会を、全くの絵空事として片づけることはできない。それは、モニターに映し出される範囲内で、インターネットが広大な仮想世界へと私たちの認識の風景を拡大してくれる現在の電子技術との親近性であり、あるいは、CTスキャンやMRAなどの電子医療技術によって脳や内臓の見えない領域がデジタル・イメージとして可視化される、現在の電子技術と肉体イメージの結びつきである。今日の私たちは、それを意識しているにせよいないにせよ、ギブソンの小説世界の中で展開されるイメージに重なる電脳社会を生きている。 現実に、その電脳社会を彩るデジタル・イメージは、ビルの壁面に設置された大スクリーンに映し出される映像のような公共空間のデジタル・イメージから、室内の私的空間のテレビ・雑誌・新聞のなかのデジタル・イメージに至るまで、すでに風景の一部として馴染み深いものになっている。また、パソコンがインターネットに接続されることによって、コミュニケーションの範囲と速度は激変したわけであるが、ネット上からは見えにくい未入力情報系の問題を考えずに、入力済み情報からなるサイバースペースだけに限定して考えたとしても、それは果てを見通すことが不可能な巨大な世界である。その巨大な情報空間に入り込み、膨大な情報の生産あるいは消費をするためには、キーボードを打つ指先とマウスを動かす指の腹と掌の操作ていどの、最小限の身体操作があればよい。 そのような環境と身体性との関わりにおいて、デジタル情報の記録媒体として利用されているCD-ROMに興味深い例が見受けられる。CD-ROMで制作されたマービン・ミンスキー『心の社会』(Voyger、1994)やローリー・アンダーソン『パペット・モーテル』(Voyger、1995)では、電子テクストのデジタル空間やCG映像の疑似空間に本人の実写映像が使用されている。これは、デジタル情報による巨大な疑似空間への出入りが身体的には指先の手触り程度の皮膚感覚しか要さないにも関わらず、身体の全体性が映像として残存しているということなのである。 修正・改変が容易であるデジタル・イメージによって重ね貼りされた情報環境では、もはや「百聞は一見にしかず」という諺は当てはまらない。イメージの力が強大なものだからこそ、イメージのはたらきの生成のプロセスを積極的に見極めていくことが求められるのではあるが、目は騙されるのである。このようなデジタル環境において私たちの認識の基盤を、たとえ暫定的ではあれ、どこにおけばよいのだろうか。外界に対して目を見開きながらも、目だけに頼るということを控えるという姿勢だけでは不十分であると認めざるを得ない。そこで、私たちの認識の舞台の前景にそっと登場するのが、手触りという身体感覚ではないだろうか。 1999年8月1日 長畑 明利 古来より、詩人の想像力は、詩人自らの「自己」を超越して、「他者」の自己を纏う、あるいは「他者に成り代わって語る」という願望を実現してきた。しかし、今世紀のアメリカを中心とする詩人たち、ことにアヴァンギャルドの詩人たちは、「他者のアイデンティティを纏う」というこの試みを以前にも増して意識的に問題化し、様々な手法的実験のうちにそれを実践してきたように思われる。その一例として、偽の被爆者詩人Araki Yasusada の事件のあらましを紹介したい。 この事件は1995年前後に起きた。広島で被爆したという日本人の詩人アラキ・ヤスサダの遺稿とされるものが、アメリカの詩に関するいくつかの雑誌に掲載されたのである。いずれのテクストも3人の日本人が翻訳したことになっており、テクストに先立って、この翻訳者たちによるアラキ・ヤスサダの略歴が付されていた。その内容をまとめると次のようになる。 アラキ・ヤスサダは1907年に京都市で生まれ、1921年に家族とともに広島に移った。彼は1925年から1928年まで広島大学に通ったが、父親の病気のために、大学を中退し、郵便局に就職せざるを得なくなった。1930年に結婚。妻との間に二人の娘と一人の息子をもうける。1936年に召集されて日本帝国陸軍に入隊、軍逓信部の事務員として勤務。1945年8月6日の原子爆弾の炸裂で妻と末娘のチエコは即死。娘のアキコは生き延びたが放射能の病気で4年と経たぬうちに死亡。まだ小さかった息子のヤスナリは親戚とともに広島市外にいた。その後、ヤスサダは1972年に癌により死亡。そのヤスサダのノートが彼の息子によって発見されたのは1980年のことである。ノートから判断すると、ヤスサダは、荻原井泉水や種田山頭火といった著名な作家や芸術家の知り合いであったが、彼の作品は生前ほとんど知られていなかった。 こうした内容の紹介文とともに、ケロイドの痕を見せるヤスサダの顔のスケッチが掲載されており、読者にヤスサダの実在性を訴えかける仕組みとなっている。 ヤスサダの遺稿とされるテクストは、詩だけでなく、手紙のコピーや、禅問答の記録、英語の宿題その他の混在したものだが、それらは、偽物であることを知らずに読んでも十分面白いものと言える。手紙の次に詩が、次に禅の文句が、次には俳句が並ぶというスタイルは、どことなくパウンドのマラテスタ・カントーズを思わせないでもない。また、作品としての詩だけでなく、その原稿やメモなどをも作品と一緒に並べる手法は、いわばドキュメンタリー的錯覚を与えている。詩は、「言語詩」風のいかにも前衛的なものもあるが、全体的には平明で、広島での被爆体験を告白スタイルで表現したもの少なくない。全体的にオリエンタリズムが濃厚であり、アジア系アメリカ人の批評家たちからはこの点を批判されている。 ヤスサダのテクストは、最初は比較的マイナーな雑誌に掲載されたのだが、電子メイルによるディスカッションリストなどを通して、素晴らしい才能の感動的な詩テクストが発掘されたという噂が拡がっていった。1996年には詩の雑誌としてはメジャーの『アメリカン・ポエトリー・レヴュー』(APR)誌が、"Doubled Flowering: Fromthe Notebooks of Araki Yasusada" と題した特集を組むまでになる。しかしAPR誌の特集が出る以前から、ヤスサダのテクストは偽物ではないかという噂が流れていた。その根拠は次のようなものである。 (1) ヤスサダの遺稿を英語に翻訳したことになっている3人の日本人の名前は、トサ・モトキユ、オークラ・キョジン、オジウ・ノリナガとされている。これは有り得ないわけではないが、かなり珍しい名前ではある。(2) ヤスサダの妻はアラキ・ノムラという名前だと言うが、この名前も不自然である。(3) ヤスサダは戦前に広島大学で学んだというが、広島大学の設立は戦後である。(4) ヤスサダはフランスの哲学者ロラン・バルトの『表徴の帝国』を1967年に読んだことになっているが、この本は1970年の出版である。(5) 遺稿の中には、ヤスサダが俳人の種田山頭火と一緒に写っている写真があるとされているが、その写真の現物が日本から送られる際に紛失したとされているのも不自然である。 こうした指摘を受けて、1997年に、編集者と翻訳者の間を取り持っていたとされるケント・ジョンソンという詩人が、インタヴューで、アラキ・ヤスサダが虚構の人物であることを明らかにした。彼は3人の翻訳者も虚構であり、ヤスサダの遺稿を作り上げた実の作者は彼の友人である。しかしその人は、不幸にして、1996年の夏にすでに死亡している。そして遺言により、その人の真のアイデンティティを明かしてはならないことになっていると、ジョンソンは言う。ただし、ジョンソンが彼の友人であると主張するこの「真の作者」もジョンソンその人の創作なのではないか、という疑念はいまだに解消されていない。 ヤスサダの事件はホークス(hoax)というカテゴリーに入れられるものだろうが、ホークス自体は別に目新しいものではない。しかし、ヤスサダの場合はアヴァンギャルド的実験の性格が強いことを考慮に入れねばならない。その実験は、明らかに「著者」あるいは「主体」概念の解体を目的としている。ヤスサダの実験の担い手は、被爆者への共感の表明が、確固たる主体ではなく、架空の主体によっても可能であることを示そうとしている(言明に対する責任を負う主体を否定しながら、なおかつサバルタンとして捉えられた被爆者への共感を示そうとするポストモダン的試み)のだが、その試みは必ずしも成功しているようには見えない。例えば、テクストに散見される猥褻語が共感の信憑性を疑わしいものにしていることは、そのような評価を裏付けるものと言えるだろう。むしろこの実験に見るべきものは、「主体」そして「著者」というものを否定しようとする強い熱意なのではないか。そしてこの熱意の源にあると思われる「自己と他者の境界を越えようという欲求」にこそ、この実験の真の意義は見出されるのではないだろうか。 1999年8月1日 澤 正宏 《パネル・ディスカッション要旨》 1999年8月2日 小畑 精和 加藤 光也 鈴木 将久 1930年代の上海を称して、日本人は「魔都」、西洋人は「冒険家の楽園」と呼んだ。いずれも享楽的な側面を過度に強調した呼び方ではあるが、上海において都市文明の繁栄が目に付くことを表現しているとも考えられる。中国において西洋文明と接する窓口であった都市上海については、最近では「接触地帯=contact zone」の概念を用いた研究があるように、複数の文明が接触し、相互に力を及ぼしあう場であったと論じられている。上海モダニストと呼ばれる一群の作家たちは、このような、かつて中国には存在しなかったコスモポリス上海の景観と都市の関係性を、漢字を用いた書記言語である中国語によって表象しようと試みていた。 1937年8月、上海近郊で日本軍が戦端を開くと、上海で活動していた多くの文学者たちは、創作環境の不安定化を恐れ、上海を離れることを決意した。戦時首都となった重慶へ赴くもの、戦時下の文化の中心となった昆明へ向かうものなど、行き先は様々であったが、上海モダニストの多くが目指したのは、比較的上海に似た条件を有している植民都市香港であった。当時の香港は、上海に比べると文化的にも経済的に寂寞を感じたというが、そこで彼らは、新聞、雑誌などを創刊し、自らの文学活動の空間を切り開いた。 この報告では、戦時下香港における上海モダニストの活動をめぐって、二つの問いを提起したい。 第一に、戦時下における表現の可能性をめぐる問題。フランス象徴派に傾倒した詩人としても知られる戴望舒による、新聞の文芸欄の創刊宣言を読むと、彼らが、いつ到来するかわからない戦争の影に不安を感じていたことが見て取れる。その不安は、破滅への不安ではない。むしろ破滅とも安定ともはっきりしない、先の見えなさに対する不安である。また彼らは、不安に対抗する力強い表現をしたわけでもない。むしろ不安へのおののきを言語化しようと模索している。彼らは、「破滅」や「安定」いった明確な言語化ができない状態、したがって前向きな言語による宣言式の文章も書けない状況を直視しながら、形にならない茫漠とした不安を、いわば言語による定着の困難な状況を、それでも言語によって表象しようと試みていたように考えられる。 戦後日本では、竹内好をはじめとする中国文学者が、戦時中の中国において力強い抵抗の文学が産み出されていたことを発見し、驚愕した。それに比して香港におけるモダニストの表現は、いかにもひ弱で、か細い。しかし現在の日本においては、戦争体験が風化し、被侵略者への想像力という言い方が空虚なスローガンと化しつつあることを考えると、むしろ彼らのか細い声に耳を澄ますことにこそ、自らの認識を揺るがす衝撃力が秘められていると思えてならない。明確な言語による定形化をはみ出し続け、御題目の無効性を示してみせる彼らの表象は、現代人が忘却し(ようとし)ている、戦争の言語化できないまがまがしさを、告発しているのはなかろうか。 第二に、香港出身の文学者たちの声をめぐる問題。大陸から到来した文学者が開いた文学メディア上において、大陸と同時進行で、いくつかの文学論争がおこなわれた。中でも重要なのは「民族形式」論争と呼ばれる論争である。民族の気風を表現するために、中国に旧来から備わる「旧形式」を利用しなければならないと説く論争であり、いわば、ナショナル・アイデンティティ確立のため「古典」を動員し、現代的に再創造しようとする、近代世界のいたるところで遂行された運動の一つであるが、ここで注目したいのは、それが大陸と同時進行でおこなわれた結果、従来大陸の文学運動から離れた地点にいた香港の作家たちに、ナショナル・アイデンティティがもたらされたことである。 大陸作家の主導によってナショナル・アイデンティティがもたらされたことに対して、香港出身作家は軋みを発していたことが、彼らの座談会の記録に残されている。香港の青年作家たちは、どうしようもない違和感を感じながら、しかしそれを克服しなければならないと信じていた。ところが、文学メディアは大陸作家によってほぼ独占され、「修養」を続ける香港の青年作家には、作品発表の場が与えられなかった。彼らは、第一に戦争がもたらす言語化困難な不安によって、次に大陸作家の独占的な声によって、二重に、発声の困難な位置に追いやられていたと言えるだろう。しかも、戦時中の香港作家が体験したアイデンティティ・ポリティクスの複雑な葛藤は、現在の香港にまで及んでいると考えられる。葛藤するアイデンティティの力学を見事に理論化したレイ・チョウの著作を読むとき、その思考の根源にある戦時下香港の境遇に、思いを馳せずにはいられない。 高橋 世織 《研究会発表要旨》 1999年12月19日 岡倉天心とインド--越境する近代国民意識と汎アジア・イデオロギーの帰趨 稲賀 繁美 岡倉天心(1862-1913)の著作、とりわけ『東洋の理想』(1904)と、生前未刊の草稿で通称『東洋の覚醒』を、天心の第1次ベンガル滞在(1901-02)との関連で分析する。まず天心のインド旅行と、ヒンディズムの近代的再興の中心人物ヴィヴェカーナンダ(1864-1902)との出会いの媒介となったジョセフィーヌ・マクラウド(1856-1948)、さらに天心の草稿に筆を加え、出版を取り図ったシスター・ニヴェディータ、本名マーガリット・エリザベス・ノーブル(1864-1911)の役割を検討した。マクラウドなくして天心のヴィヴェカーナンダとの出会いなく、またニヴェデイータなくして今日しられるような『東洋の理想』も存在しなかったといってよい。本件にはすでに堀岡寿美子、岡倉古志郎らによる先行研究が知られるが、今回はマクラウドの伝記、ニヴェディータの『書簡集』を利用して、東洋文化に帰依しその伝導者となった白人女性という存在に注目した。ヴィヴェカーナンダのシカゴ万国博覧会(1892)での伝説的な成功に肖り、第2回目の「世界宗教会議」を画策した天心の企ては失敗に終わるが、天心のセントルイス万国博覧会での講演(1904)には、両者に通底する思想的基盤が見える。 天心の『東洋の理想』には、ヴィヴェカーナンダの不二一元論advitismの考えを強引に東洋美術の歴史的伝播に引き付けて解釈した面が窺われる。有名な「アジアはひとつ」もこの文脈で理解できるが、そこにはまた東洋の立憲君主制独立国としての日本と、ベンガル分割令(1905)によって遠からず分割の運命を辿ろうとしていた植民地インドとの対比が、政治的な意図としても反映している。天心のインド滞在中の執筆になる『東洋の覚醒』の草稿「我らはひとつ」は、なによりもまずこうした状況に置かれていたインドの知識人たちとの連帯を謳いあげる天心のアジテイションだった。しかしこの原稿は、日露戦争を経て日本が列強の仲間入りをし、天心自身もそうした『日本の覚醒』(1905)を擁護する論陣を欧米の読者に向けて説くにおよんでは、もはや出版の可能性もなくなった。それが皇紀二千六百年の前年(1939)に『東洋の覚醒』として復活したのは、まさに亡霊の蘇りといってよい現象だった。 一方、おりからのスワデシ運動でインドにおける国民主義的なイデオロギーが高揚した20世紀初頭、『東洋の理想』は、インド美術史記述にインド中心史観を齎すうえで先駆的な役割を果たす。E.B.ハベルの一連の著作、とりわけ『インド美術の理想』への天心の感化は明白だが、A.クーマラスワーミーの初期著作も含めて、1910年代にはインド美術の独自性を、ヴェーダンタ哲学との関連で説く潮流が大きくなる。そのなかで、ガンダーラ美術をグレコ・ロマンのカノンの影響ゆえに高く評価してきたそれまでの論調は転換を迫られる。だが同時代の研究動向を総合したV.スミスの著作では、ガンダーラに中国の影を見る天心の説は、思想的影響力はとにかく、学説としては検証に耐えない謬見との烙印を押されることになる。 日本でもその晩年以降、イデオローグとしての天心像が定着するのとは裏腹に、美術史研究の世界では、天心はもはや時代遅れの先駆者として厄介払いされた傾向が見られる。1900年パリ万国博覧会のために準備されたHistoire de l'art du Japonは、天心が編集を離れてのち、水戸国学寄りの枠組みに修正された、との仮説(小路田泰直)もある。当時の腹心、伊東忠太は、同書日本語版『稿本日本帝国美術略記』(1916)では建築の部をそれ以外の分野から切り離し、いわば建築史学の独立宣言を行う。またかつての腹心、大村西崖は、天心と袂を分かって後、『審美大観』、『東洋美術大観』の膨大な編集を経て、実証的な中国美術研究の礎を築く。また東京大学初代の美術史講座教授に就任(1911)した、滝精一は、天心設立の美術研究誌『国華』の編集を襲いながら、天心没後の号(1913)では、追悼記事の代わりに、天心らによる日本美術院の試みを「失敗」と詰る、誹謗中傷の無署名記事を掲載する。天心がその思想的な基礎を築いた東洋美術という枠組みがその次ぎの世代によって制度として継承されたとき、創設者はいわば「父親殺し」よろしく葬りさられた、といっても過言ではなかろう。 講演要旨 1999年12月18日 1999年12月の合宿には、神戸市外国語大学の崎山政毅氏と多摩美術大学の港千尋氏をお迎えして、ご講演をいただいた。以下はその要旨である。 崎山 政毅 港 千尋 幹事 西 成彦 「1.20世紀における表現とディアスポラ状況」と「2.越境と文化アイデンティティー」の二つは、みなさんもすでにお気づきの通り、同じ貨幣の表と裏のようなものです。20世紀の歴史は、地球上のディアスポラ状況を加速させはしましたが、一方で、いびつなナショナリズムやネオ帝国主義の成立を促した世紀でもありました。ボーダレスな文学を志向したモダニズム芸術が、それでもなおさまざまな「国境紛争」と無縁ではいられない。むしろモダニズム芸術であればあっただけ、あらゆる「国境紛争」の当事者でありうる。そういった共通認識の下で、モダニズムがどこの程度まで「国境」から自由でありえたのか?この問題を複数の入口からアプローチしてみたい。この問題への入口の複数性を保証するための便宜的な「二つの入口」として、この二テーマを手がかりにしていただけばいいと思います。札幌では参加者の中で「1」あるいは「2」に近い関心をお持ちの方々に集まっていただき、意見の交換をしましたが、グループの参加メンバーは固定しないということに決まりました。この総合研究を出版する計画が具体的に動き出した段階で、章割や分冊の形式についてはあらためてゼロから検討し直すということです。 第2章 越境と文化アイデンティティー――あるいは〈越境〉とは何か 三宅 昭良 〈越境〉とは何か。なぜ我々は〈越境〉を問題にするのか。 われわれの活動を振り返っておこう。われわれモダニズム研究会は第二期目の研究活動を立ち上げるべく1997年5月30日に任意の会合を開き、9月の科研費申請に向けて会員の参加の確認、新会員の募集、テーマの設定など、具体的に動きはじめた。当初、テーマは(文学・芸術を中心軸とした)「20世紀の表象文化の総括」というふうに仮に設定され、これを詰めてゆく方向でスタートした。大平代表と和田さん、西さん、それに私のあいだで意見を交換して、最終的には代表が筆舌しがたい労苦のすえに、「総合研究:20世紀アヴァンギャルド諸潮流と表象文化の現在----モダンから越境へ」というタイトルにまとめて科研費申請を果たし、それは見事審査を通過し98年から本格的に共同研究を開始したのだった。 〈越境〉とはなにか。なぜわれわれはここ日本において〈越境〉を問い、日本語で語るのか。 それは研究プロジェクトからはじまった。共同研究の方式として、前回は各国別の構成をとったが、今回は複数の研究プロジェクトを立ち上げることにした。既成の研究領域を横断し、相互乗り入れし、良い意味でたがいのフィールドを侵犯しあう関係をつくれれば、という意図だったと思う。去年の夏、箱根で行なった合宿で以上のような方向を確認し、12月の神戸合宿で具体的な立案にはいることを決めたのだった。神戸では西さんの示した三つのプロジェクト案と、それと対になるような芸術内在的原理を議論するうちに、〈越境〉の一語が統一テーマとして浮上したのだった。そしてその時の議論では、ふたつのレベル----社会的文化的レベルと芸術内在的原理のレベル----における、それぞれ位相を異にする〈越境〉を結ぶものとして、創造行為における(あるいは出来上がった作品における)<身体性>の問題を位置づけたのだった。そして内在的原理のテーマについて大平代表が「イメージ・空間・身体」という括り方を提案され、この線でこの切り口をもっと深めてゆこうということが確認された。そしてメンバーから各自の執筆計画のアンケートをとり、今年の二月に高橋、西、和田、大平の各氏、それに私の五名による編集委員会を経て、現在のような五つのプロジェクトが立ち並んだわけである。 あなたにとって〈越境〉とはなにか。あなたは本当に〈越境〉を語りたいのか。 われわれの研究対象について考えてみよう。いっぽうにはパウンドやジョイスなどのように、内発的衝迫力に突き動かされ海をこえ国境を越えて創作に挑戦したものたちがいる。他方にはナボコフやブロツキーやユダヤ系の作家たちのように、状況によって他国への亡命と越境を余儀なくされたものたちがいる。それからまた、芸術家個人の経験ではなく、世界規模におけるディアスポラ状況のなかで、作品にそうした状況を反映させるものたちもいる。はたまた生まれたときに、すでにディアスポラを生きるべく運命づけられた作家や詩人、芸術家もいよう。私が今回取り組むデレク・ウォルコットや、岡さんが話されもしかすると崎山さんがテーマとするであろうサバルタンの作家たちを、そのように見ることが可能かも知れない。坂田さんがとりあげようとしている女性作家たちもまた、同じように位置づけられるであろう。また長畑さんが先回の発表であつかったような騙る越境もある。問題はそのように多種多様な個別的ディアスポラ状況のありようを、<越境>の一語で括ったときに何が見えてくるかである。何が見えてくるのであろう。 今回のプロジェクトには第1、2章の「ディアスポラ/越境」テーマ、第3章の「権力と芸術」とは別に、「モダニズム/アヴァンギャルド表現の再検証」、「表象からの越境」の二章が立てられている。これら二章と前三章はどう切り結べばよいのか。言葉をかえて同じことを問おう。状況内的越境と芸術内在的越境は相互にディアスポラ/越境しないでよいのか。われわれの成果発表の形式をどうするか、一冊本で行くか分冊形式で行くか、まだ結論は出ていないが、いずれにしろ、ふたつの<越境>が相互に関連性を見いだされないままに終わったのでは、この共同研究は失敗であったという批判があれば、われわれはそれを甘んじて受け入れなければならないであろう。 ここで愚見を述べることがゆるされるなら、当会の意義は、越境/ディアスポラ/クレオールというタームで「状況」を語ることに傾きがちである日本において、同様の言葉で同じ問題を扱いながら、作品の内的原理にまでおりていって議論するところにあるだろう。そしてまた、逆の構図、すなわち二〇世紀的世界的ディアスポラ状況のなかで個々の作品の内的原理を再検証するという構図も、これまで日本において行なわれてこなかったことであろう。つまり、状況内的越境をあつかう際、われわれは芸術内在的原理としての越境を問題にせずにはすまされないし、逆もまた然りなのである。そうでなければわれわれの<越境>は、当世はやりの知的トレンドに便乗した凡庸な成果のひとつとして出版の洪水のなかにかき消えるほかないだろう。そうならないためにも我々は、公開シンポジウムの前にここでであらためて「越境とは何か」を議論して、共通理解を深めておく必要があるだろう。そこで実り多い議論がなされ、その果実が各自の論文に活かされたならば、真の意味で文化貢献的な<越境>をめぐる一大パノラマを世に問うことができるだろう。編集幹事のひとりとして、私は以上のようなことを愚考する次第である。 いささか時代錯誤的アジ演説調の一文になってしまったこと、趣味の悪さをなにとぞお許しください。 幹事 和田 忠彦 第4章 モダニズム/アヴァンギャルド表現の再検証:概要とコメント 幹事 大平 具彦 第4章は、タイトルの示す通り、他の章のテーマから一応独立する形で、モノグラフ的にある作家なりある特定の事例を取り上げて、モダニズムあるいはアヴァンギャルドの諸相を今日的視点から検証しようとするものです。この章の執筆者(敬称略)と論題は、目下のところ下記の通りです。
他の章には求心的な共通軸が立てられているのに対し、この章には<モダニズム/アヴァンギャルド表現の再検証>というゆるやかな括り方があるだけです。まとめ役の幹事としては、これは、ある面では確かに弱味かもしれませんが、他の面から見れば強味にもなり得るものと考えています。そのためには、それぞれの論考が、個々の作家や事例それ自体の圏内だけで語られるのでなく(その場合は他のテーマには属さないというためだけのグルーピングにとどまってしまいます)、彼ら(それら)を通して、モダニズム/アヴァンギャルドの諸々の局面が先鋭に浮かび上がってくるように方向づけられている必要がありましょう。それがうまく成功すれば、他の章を別の面から照らし出すユニークな章になることも可能でしょう。各執筆者の方々、こうした方向性について(その内容については今後さらに討議を通して肉付けされるべきですが)、どうぞご理解とご協力をお願いいたします。ふたつの民族の記憶と記憶がぶつかりあう。 幹事 高橋 世織 |